丸の内線 東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分
 03-3311-4811
03-3311-4811
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
 03-3311-4811
03-3311-4811
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗鬆症」といいます。
骨粗鬆症により骨がもろくなると、つまずいて手や肘をついたり、くしゃみをしたりなどのわずかな衝撃で骨折してしまうことがあります。
がんや脳卒中、心筋梗塞のように直接的に生命をおびやかす病気ではありませんが、骨粗鬆症による骨折から、介護が必要になってしまう人も少なくありません。
骨粗鬆症は痛みなどの自覚症状がないことが多く、定期的に骨密度検査を受けるなど日ごろから細やかなチェックが必要です。

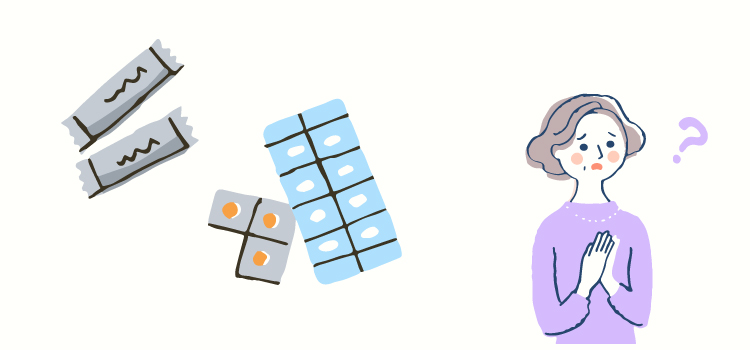
骨粗鬆症は、その原因により大きく2つのタイプに分けられます。
1つめは、おもに加齢によって引き起こされるタイプです。これを「原発性骨粗鬆症」といい、骨粗鬆症の多くはこのタイプです。
2つめは、病気や薬の影響で二次的に起こるタイプで、これを「続発性骨粗鬆症」といいます。
続発性骨粗鬆症の場合、まずは原因となる病気の治療や、服用している薬の中止・減量などを検討しなければいけません。
そのため、骨粗鬆症が疑われる場合には、どのような原因で発症しているのかを調べ、原発性と続発性との判別を行う必要があります。
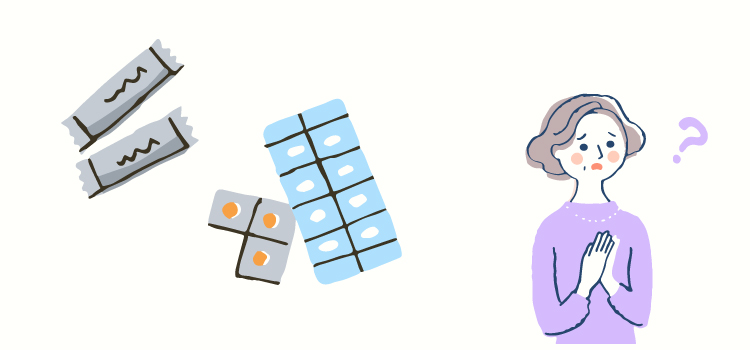
原因となる病気などがなく、加齢や閉経にともなって引き起こされる骨粗鬆症です。
男性にもみられますが、閉経による女性ホルモンの分泌低下が骨密度を低下させることが知られており、特に女性に多くなります。
そのため患者さまの男女比は、男性と比べて女性の患者数が約3倍多いと言われています。
こうした生理的な体の変化に加え、遺伝的要因や栄養不良、体を動かさずに過ごすといった生活習慣も、骨粗鬆症の発症に大きく関係していることが分かっています。
原発性骨粗鬆症は、加齢、女性ホルモンの低下、不摂生な生活習慣などが引き金となって発症する骨粗鬆症を言います。

骨密度は18歳~20歳くらいでピークに達します。
そののち40歳代半ばまではほぼ一定ですが、50歳前後から急速に低下していきます。
骨をつくるのに必要なカルシウムは、腸から吸収されて骨に取り込まれますが、年を取ると腸からのカルシウム吸収が悪くなり、吸収が落ちると骨リモデリング(新しい骨をつくる代謝作用)のスピードが落ちるようになります。
これにより骨形成のスピードも低下させるようになることから、骨がもろくなり骨粗鬆症を発症させやすくします。
女性の多くは更年期(45~55歳)の年代になると閉経を迎えるようになり、閉経後はエストロゲンという女性ホルモンの一種が著しく減少するようになります。
エストロゲンには骨の新陳代謝に対して骨吸収のスピードを緩める成分が含まれ、エストロゲンが分泌されなくなると一気に骨吸収のスピードは加速し、骨形成が追い付かなくなっていきます。
そして次第に骨はスカスカの状態になってしまい折れやすくなっていきます。
女性ホルモンの減少が主な原因となっている骨粗鬆症に対しては、女性ホルモンやそれに似た作用のある薬、骨密度を増やす薬などが用いられます。
ダイエットによる栄養不足は、骨粗鬆症の原因の1つとなります。
とくに成長期は丈夫な骨をつくる大事な時期ですので、無理なダイエットは将来の骨密度に悪影響を与えます。
成長期にはカルシウムを十分に摂り、他の栄養素もバランスよく摂取するなど、よい食生活の習慣を保つことで、骨密度を高く保つことができます。

このように原発性骨粗鬆症の患者さまは、老人性骨粗鬆症と閉経後骨粗鬆症、ダイエットによる栄養不足の患者さまでほぼ占められていますが、 そのほかにも日頃の不摂生な生活習慣(食生活の乱れ、運動不足、寝たきりなど)などで骨量を低下させて発症するケースもあります。
特定の病気や、服用している薬が原因となって骨強度が低下する骨粗鬆症です。
原因となる病気としては、副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、関節リウマチのほか、動脈硬化やCKD(慢性腎臓病)、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、糖尿病などの生活習慣病で頻度が高いとされています。
これらの病気では、骨代謝に影響を及ぼすホルモンが不足したり、骨形成に必要な細胞などに異常が起こったりして骨量が減るものもありますが、骨の中に骨質を劣化させる物質が増えて骨がもろくなってしまうものもあります。
薬の副作用による骨粗鬆症では、代表的なものにはステロイド薬の長期服用があります。

生活習慣病はご存知のとおり、食習慣や運動不足などのライフスタイルをおもな原因として起こる病気です。
高血圧や脂質異常症、糖尿病などがその代表格として知られており、最近ではCOPD(慢性閉塞性肺疾患)や、成人の8人に1人が発症していると言われるCKD(慢性腎臓病)なども注目されているところです。中高年になると、「生活習慣病と骨粗鬆症の両方を治療中」という人もおられるでしょう。この2つの病気に関連があると考える人は少ないかもしれませんが、最近では、生活習慣病が骨代謝に影響を及ぼすことが明らかとなってきています。なかでも糖尿病とCKDは、骨粗鬆症と密接な関連があるとして注目されています。
こうした生活習慣病関連骨粗鬆症では、骨密度が正常に保たれているケースもあり、それでも骨折を生じやすいのは骨質劣化の関与が大きいと考えられています。
薬による続発性骨粗鬆症のうち、代表的なものがステロイド性骨粗鬆症です。
ステロイド薬の投与開始後、3ヵ月以内で骨への影響が現れ、長期間使用している方の50%で骨粗鬆症を発症しているという報告もあるほどです。ステロイド薬を長期使用する病気では、関節リウマチや気管支喘息、膠原病をはじめとする自己免疫疾患などが挙げられます。
これらの病気では、薬の影響だけでなく、例えば関節リウマチでは骨や軟骨が破壊されるように、病気そのものが骨に影響を及ぼしているケースも少なくありません。
ステロイド性骨粗鬆症は骨折リスクが高いため、原発性骨粗鬆症の場合よりも、骨密度が高いうちから治療を開始することが推奨されています。
当院の骨密度検査方法では、正確な数値に基づき患者さまに的確な診断とアドバイスを行うためにDXA法を採用しています。
DXA法は体のあらゆる部位の骨密度を最も正確に測定できると言われています。しかし、的確な診断には一つの結果だけでなく、多角的な視点からの総合的な判断が必要です。
そのため血液検査、尿検査も実施しております。

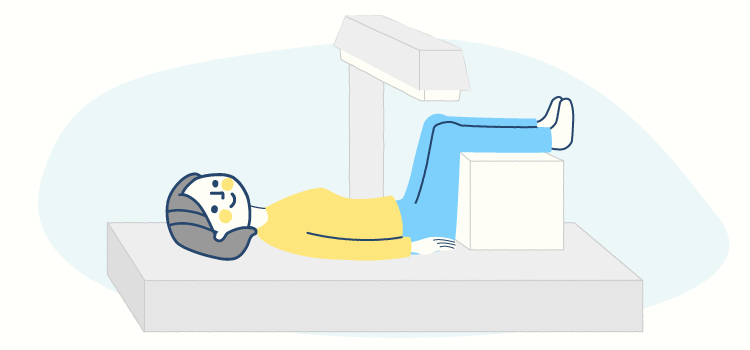
エネルギーの低い2種類のエックス線を用いて骨量を測定する方法です。
全身のほとんどの骨を測ることができます。
腰の骨(腰椎)や太もものつけ根(大腿骨近位部)、ひじから手首までの前腕の親指側にある細長い骨(橈骨 とうこつ)を測定し、得られる数値が正確なので骨粗鬆症の診断に使用されています。

骨の新陳代謝の過程で出現する物質を骨代謝マーカーといいます。
骨代謝マーカーは血液検査や尿検査によって測定され、骨の新陳代謝の速度を知ることができます。
骨吸収を示す骨代謝マーカーの高い人は骨密度の低下速度が速いことから、骨密度の値にかかわらず骨折の危険性が高くなっています。
この検査は、骨粗鬆症と他の病気を区別するためにも行われます。
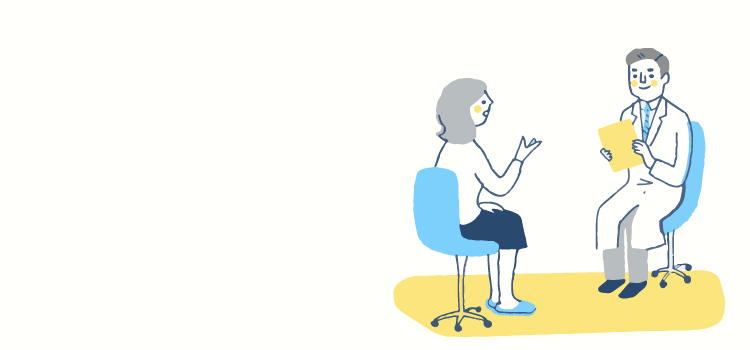
検査そのものは20分~30分程度で全て終わります。
血液検査は結果が出るまで1週間程度かかります。
そのため、検査日から1週間以降で再診をお願いしています。
再診時に検査結果をもとに、患者さまに適した治療法や生活習慣の改善アドバイスをお伝えいたします。
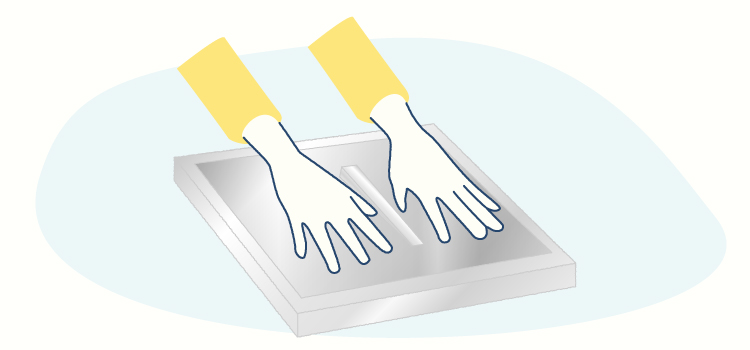
エックス線を使って、骨とアルミニウムの濃度を比べることによって測定します。
手と、手の骨と厚さの異なるアルミニウム板を同時にエックス線写真を撮影し、画像の濃淡の差をコンピューターに読み取らせて解析する方法です。
MD法の測定対象である第2中手骨がもともと骨皮質の割合が多い骨のため、早期の骨密度の減少が反映されにくいと言われています。また、薬物治療の効果判定も測定値に反映されにくいなどのデメリットがあります。
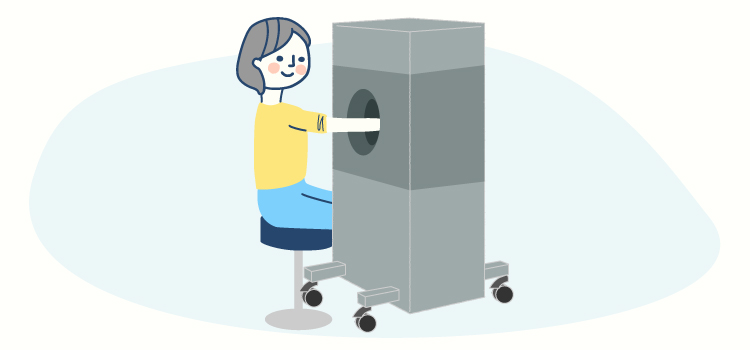
CTを用いて算出する方法で、腰(腰椎)の3次元的な骨量を測定できます。
ただし、DXA法に比べて放射線被ばくがやや多い方法です。

超音波の伝搬速度を用いて骨を評価する方法で、通常は踵(かかと)やすねの骨を用いて測定します。
放射線を使用しないため、人間ドックや検診には汎用されていますが、骨量そのものを測定しているわけではありませんので診断には用いません。
主に背骨(胸椎や腰椎)のエックス線写真を撮り、骨折や変形の有無、骨粗鬆症の程度を確認します。
圧迫骨折にもさまざまな形があります。
前方や真ん中がへこんだもの、全体的に薄くなったものなど、元の高さより20%以上減っているものを圧迫骨折と判定します。
骨粗鬆症と他の病気とを区別するためにも必要な検査です。
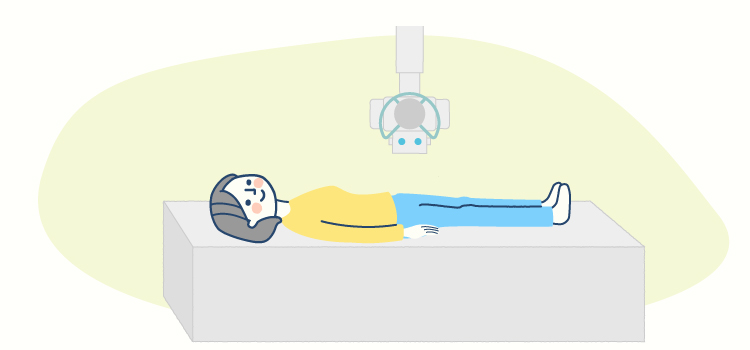
骨密度と骨のもろさ、転倒やちょっとした衝撃で生じた骨折(脆弱性骨折 ぜいじゃくせいこっせつ)があるかどうかの3つが重要です。
脆弱性骨折には、本人が自覚していない間に生じる骨折もあり、診断のためにはレントゲン検査が必要となります。
脆弱性骨折がある人で、それが椎体骨折または大腿骨近位部骨折の場合、もしくはその他の脆弱性骨折があり、骨密度がYAM(※1)の70%未満の場合、骨粗鬆症と診断します。
脆弱性骨折がない人でも、骨密度がYAM70%以下または-2.5SD(※2)以下であれば骨粗鬆症と診断します。
CTを用いて算出する方法で腰(腰椎)の3次元的な骨量を測定できます。
ただし、DXA法に比べて放射線被ばくがやや多い方法です。
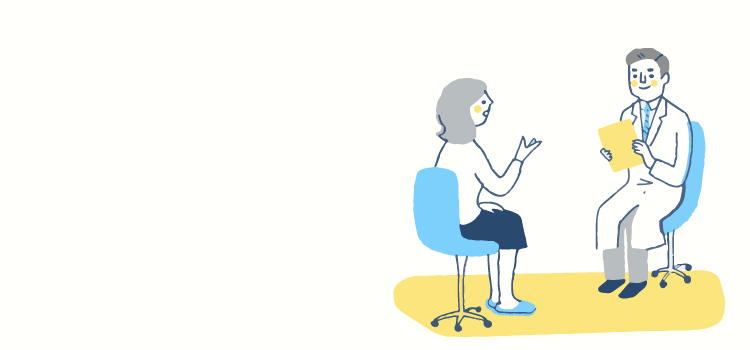

骨粗鬆症の発病には、加齢や閉経以外にも食事や運動の習慣などが深く関わっています。
そのため骨の生活習慣病とも呼ばれ、食事療法や運動療法も骨粗鬆症の予防には欠かせません。
カルシウム、ビタミンD、ビタミンKなど骨の形成に役立つ栄養素を積極的に摂ることが推奨されています。
カルシウムとビタミンDを同時に摂ることで、腸管でのカルシウム吸収率がよくなります。
また、高齢になると食の好みが変わったり、食が細くなるなどしてタンパク質の摂取量は不足する傾向があります。
タンパク質の摂取量が少ないと骨密度低下を助長しますので、意識して摂取するのが良いでしょう。
栄養やカロリーのバランスがよい食事を規則的に摂るのが、食事療法の基本です。
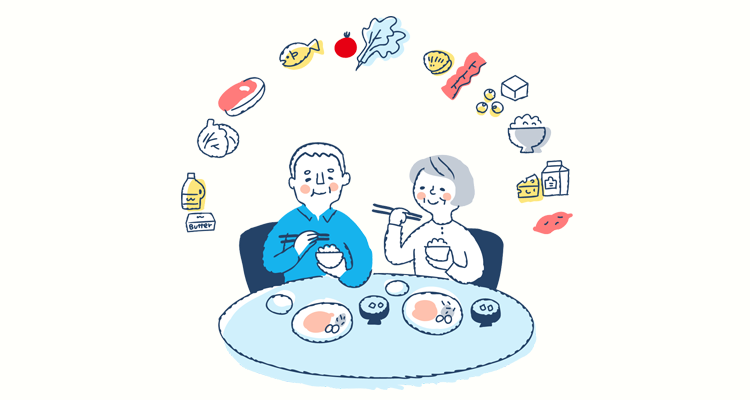
牛乳・乳製品、小魚、干しエビ、小松菜、チンゲン菜、大豆製品など
※骨粗鬆症や骨折予防のためのカルシウムの摂取推奨量は、1日700~800㎎と言われています。
サケ、ウナギ、サンマ、メカジキ、イサキ、カレイ、シイタケ、キクラゲ、卵など
納豆、ホウレン草、小松菜、ニラ、ブロッコリー、サニーレタス、キャベツなど
カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、紫外線を浴びることで体内でつくられます。
直射日光を長時間浴びることは、皮膚が赤くなるなどダメージにつながりますが、適度な日光浴は骨の健康に役立ちます。
冬であれば30分~1時間程度散歩に出かけたり、夏であれば暑さを避けて木陰で30分程度過ごすだけで十分です。
屋内で過ごす時間が長い高齢者や、美容のために過度な紫外線対策を行っている人では、ビタミンD不足が心配されます。
運動をかねて積極的に外出する機会をつくるのが良いでしょう。

骨は、負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり強くなる性質があります。
散歩をしたり、階段の上り下りなど、日常生活のなかで無理のない範囲で運動量を増やしましょう。
骨折予防に有効な運動は、ウォーキング、ジョギング、エクササイズなどがありますが、ご自身の体の状態にあわせて無理なく継続することが大切です。骨粗鬆症治療中の方や膝に痛みがある方は、運動を開始する前に医師に相談してください。ここでは家の中でも手軽に行えて、骨密度低下防止に効果的な運動を紹介します。


目を開けた状態で片脚で立ちます。不安な方は壁やテーブルにつかまりながら行ってもかまいません。
体重を片脚に乗せることで、両脚立ちの倍の負荷を与えることができ、骨を強くする効果を期待します。
バランス感覚が養え、転倒予防にもなります。

壁に手をついて、体を支えながらふくらはぎとアキレス腱を伸ばします。前に出した方の脚の膝を曲げて徐々に体重をかけていき、後ろ側の脚のふくらはぎを伸ばします。
後ろの方の脚の膝を曲げ、アキレス腱を伸ばします。片脚30~40秒ずつを目安に左右交互に行いましょう。

立った姿勢で壁から20~30cm離れて立ち、壁に沿って両手をできるだけ上の方にのばします。
イスに座って頭のうしろで手を組み、両肘をできるだけうしろのほうに引き、胸を開きます。
長年住み慣れた家は安全と思いがちですが、意外にも高齢者の転倒事故の多くが、家の中で起こっています。
高齢者の転倒は、視力や筋力が衰えるなどなど身体的な原因のほか、住まいの環境や薬の副作用など様々な要素が重なり合って生じます。
若い方にとってはなんでもないわずかな段差も、高齢者にとってはつまづきの原因となることが多々あります。
骨粗鬆症の方は治療を受けることはもちろんですが、骨折のきっかけをつくらないことも重要です。
住まいも含めた身の回りをチェックして、転倒リスクが高い場所は避けるなど意識的に環境づくりをすることも大切です。
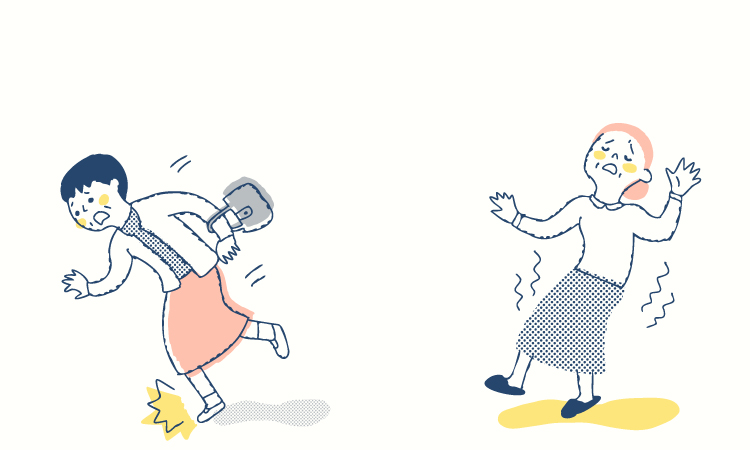
上記のように骨粗鬆症の予防のため、食事や運動も非常に大切ですが、骨粗鬆症と診断された場合には薬が治療の中心となります。
骨粗鬆症の治療薬にはそれぞれ特性があり、薬によって得意とする部位や症状が異なります。
よって、それぞれの症状をよく考え、適切な種類の治療薬を選択することが重要です。

| 分類 | 一般名 | 骨密度 | 椎体骨折 | 非椎体骨折 | 大腿骨近位部骨折 |
|---|---|---|---|---|---|
| カルシウム薬 | L-アスパラギン酸カルシウム | C | C | C | C |
| リン酸水素カルシウム | C | C | C | C | |
| 女性ホルモン薬 | エストリオール | C | C | C | C |
| エストラジオール | A | C | C | C | |
| 活性型ビタミンD3製剤 | |||||
| アルファカルシドール | B | B | B | C | |
| カルシトリオール | B | B | B | C | |
| エルデカルシトール | A | A | B | C | |
| ビタミンK2製剤 | |||||
| メナテトレノン | B | B | B | C | |
| ビスホスホネート製剤 | |||||
| エチドロン酸 | A | A | C | C | |
| アレンドロン酸 | A | A | A | A | |
| リセドロン酸 | A | A | A | A | |
| ミノドロン酸 | A | A | C | C | |
| SERM | ラロキシフェン | A | A | B | C |
| パゼドキシフェン | A | A | B | C | |
| カルシトニン薬 | エルカトニン | B | B | C | C |
| サケカルシトニン | B | B | C | C | |
| 甲状腺ホルモン薬 | |||||
| テリバラチド(遺伝子組換え) | A | A | A | C | |
| その他 | イプリフラボン | C | C | C | C |
| ナンドロロン | C | C | C | C |
活性型ビタミンD3製剤
活性型ビタミンD3製剤、ビタミンK2製剤、
テリパラチド(副甲状腺ホルモン)
女性ホルモン製剤(エストロゲン)、ビスフォスフォネート製剤、
SERM(塩酸ラロキシフェン)、カルシトニン製剤
骨粗鬆症の治療薬は、上記の他にも次々と新しいタイプの薬が登場しています。
たとえば、新しい骨をつくる骨芽細胞を活性化させ、骨強度を高める「骨形成促進薬/テリパラチド(副甲状腺ホルモン)」は、骨密度が非常に低いなど重症の患者さまに適した薬です。
現在、1日1回患者さまが自分で注射をする皮下注射剤と、週1回医療機関で皮下注射してもらうタイプとがあります。
既存の種類では、SERM(塩酸ラロキシフェン)や活性型ビタミンD3 製剤で新しい薬が登場するなど、薬物治療の選択肢が増えたといえるでしょう。
そんな中、骨粗鬆症治療においてはきちんとした服用を継続することが難しく、治療開始後1年で、患者さまの5割近くがきちんと薬を服用出来ていないというデータがあります。その原因はさまざまですが、少しでも患者さまが服用しやすくなるように、投与間隔や剤型に工夫が加えられた薬の開発も進んでいます。
たとえば、ビスフォスフォネート製剤ではこれまで主流だった週1回服用に加え、4週1回製剤(錠剤・点滴投与)が開発されました。
さらには、高齢者では錠剤が飲みにくい問題に配慮した、経口ゼリー製剤も登場しています。
当院では検査結果を詳細に検討して、それぞれの患者さまに合った治療薬を選択しています。


症状が無くても、女性は40歳を過ぎたら定期的な骨密度検査をおすすめします。
現在では40歳以降の女性を対象に5年刻みに骨密度の節目検査を行う自治体も増えています。
特に閉経後の女性は、可能であれば半年~1年に1度検査を受けるとよいと言われています。
全ての病気に共通して言えることですが、骨粗鬆症も早期発見、早期治療で適切な治療を受けることが非常に大切です。

東京メトロ 丸の内線
東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分
〒166-0012
東京都杉並区和田3丁目59−10 CTビル1・2F
※お車でご来院の際は
お近くのコインパーキングをご利用ください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |
| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | - | - |
現金のほか、以下の決済方法がご利用いただけます。
